
| びぃふりぃ |
とっぷ | 講座等案内 | 自己紹介 | リンク | |


人権運動と共に広まったコミュニケーション技術です。相手の権利を侵害することなく、対等・誠実・率直に自分の感情や要求を伝えること、そして他人からの評価によらず自分を信頼し、自分を好きになることをめざします。日常生活から市民活動や職場までさまざまな場面での人間関係の向上に役立ちます。
自分と向き合う時間を交えながら、グループで話し合ったり実際にコミュニケーション場面を演じたりして、新しい方法を学んでいきます。

アサーティブネストレーニングは、’40年代に心理学の分野で開発されましたが、広く社会にいきわたって、
発展していくきっかけとなったのは、’60年代にアメリカで起きた公民権運動です。公民権運動では、
アメリカのアフリカンアメリカン(肌の色が黒い人たち)が、人種差別に抗議して人権を保障するように求めていきました。
この運動を展開するに当たって、アフリカンアメリカンがすでに学んでいたことは、
→自尊心を奪われるままにしておいたら、傷ついたまま。
(ex.肌が黒いというだけでリンチに合う)
→自尊心を失う方法で行動を起こしても、やっぱり手痛く傷つく。
(ex.黒人が怒りにまかせて、ひとりで白人集団に殴りこんでも自分が傷つくだけ)
ということです。
そこで、使われたのがアサーティブネスです。
その内容は、
・ 相手の挑発にのらない。
・ 相手を殴らない。
・ 黒人の私を尊重するように、白人のあなたも尊重します。
(白人をやり込めることを目的としない)
ということでした。
この公民権運動は、‘64年に人種・宗教・性・出身国による差別を禁止する法律である公民権法を成立させます。
アフリカンアメリカンたちは、差別された状況の中でも、自尊心を失うことなく、自尊心を保ったまま、行動を起こすことができる、そしてその行動が自分たちの状況を、さらには社会のあり方をも変えていくことを、体験していきました。その精神は、‘70には女性解放運動、障がい者解放運動に引き継がれていきます。
現在は人間関係向上の技術として、学校・家庭・市民活動・職場など様々な場面で、また精神保健の分野でも活用されていますが、アサーティブネスの技術は、「わたしたちは自身の尊厳を取り戻すよう行動できる。また、わたしたちは、自尊心を失うことなく、自尊心を保ったまま、行動を起こすことができる。」ということを根底のところで信頼することで、生きてきます。もちろん、そこでは「私の自尊心もあなたの自尊心も同時に手に入れることができる。」ということを信頼することでもあり、相手の自尊心を尊重できるということも含まれてきます。
アサーティブネスが目指している、誠実で率直で対等なコミュニケーションというのは、こういったところから生まれてきています。
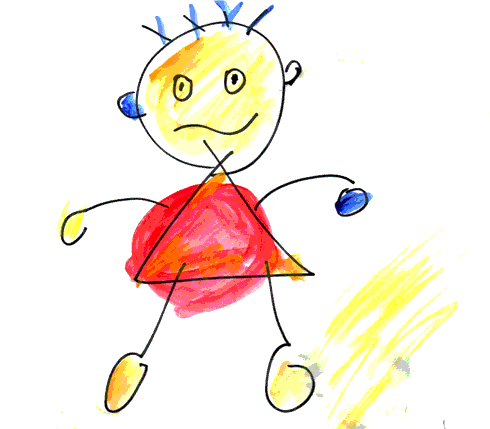
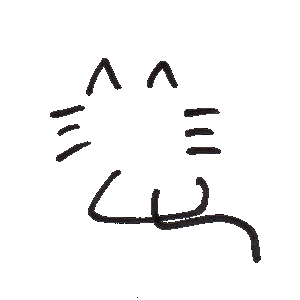
アサーティブネスは、
「みんなちがってみんないい」
ということを、具体化していくためのツールになる、と同時に
「私は、みんなとちがってそれでいい」
という、自分自身を認めていくツールになると確信しています。
びぃふりぃ 遠藤 祥子
参考文献 「こころのちから」岩井美代子著 ワニブックス
「多様性トレーニングガイド」森田ゆり著 開放出版社